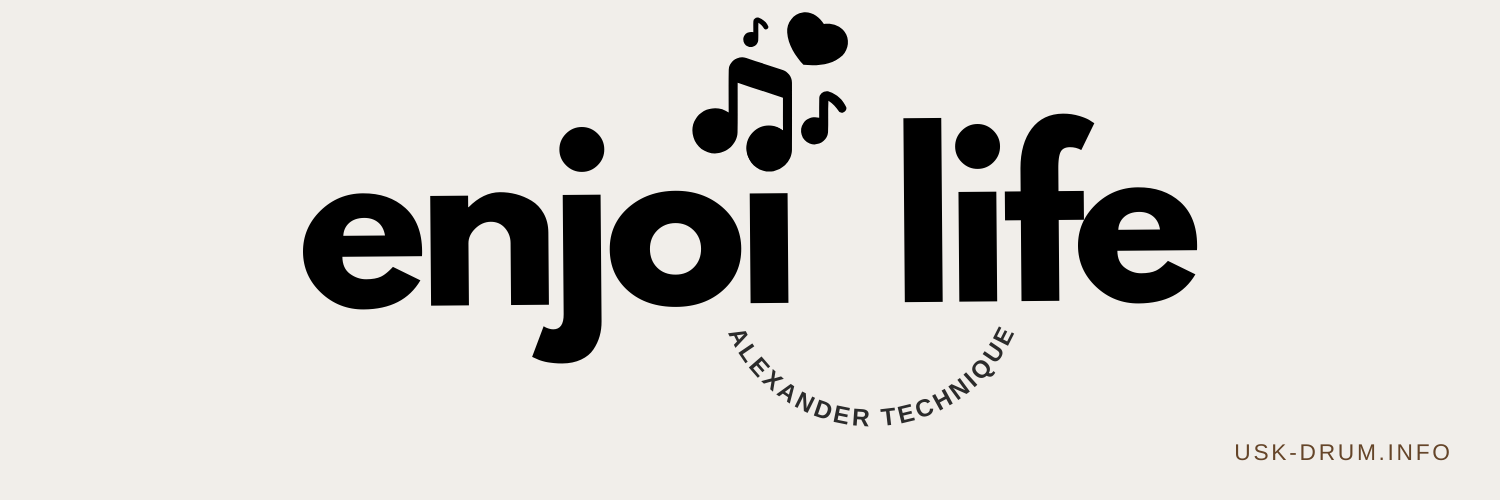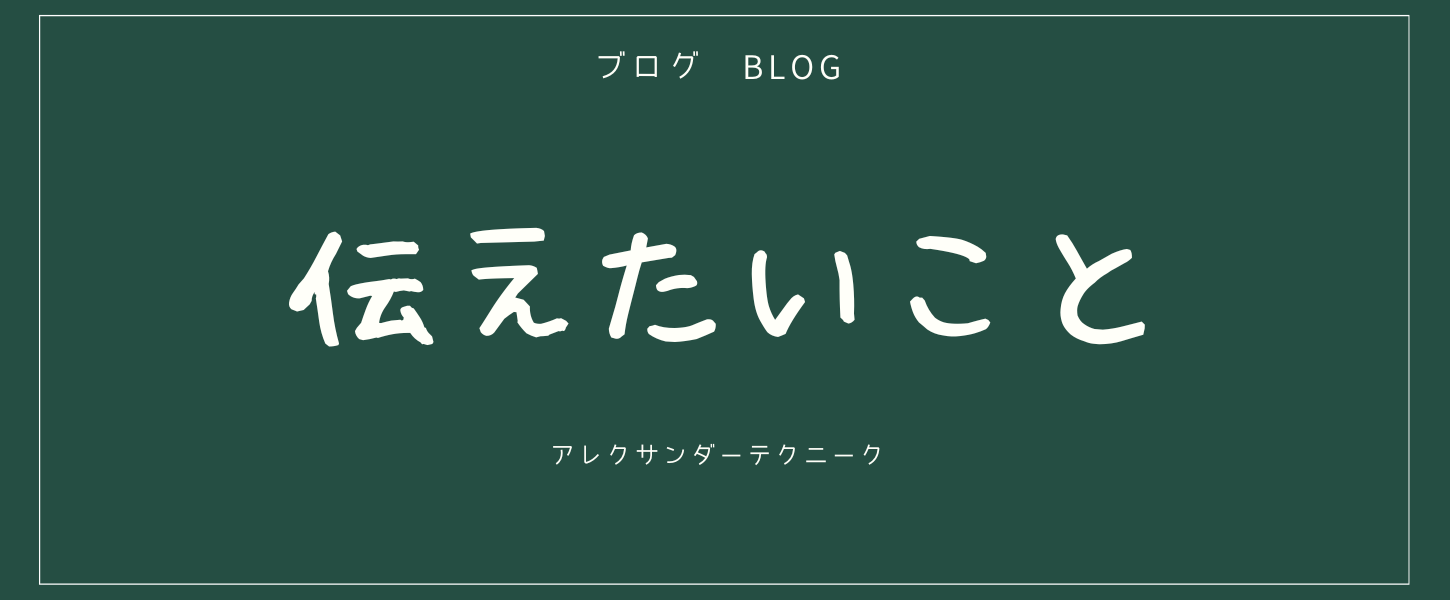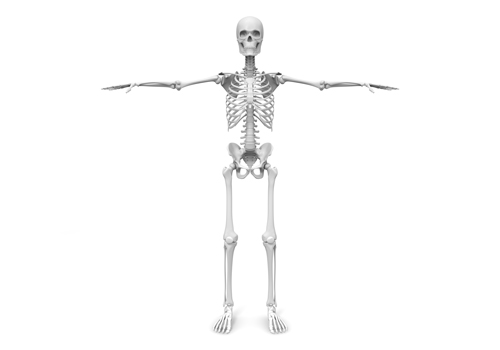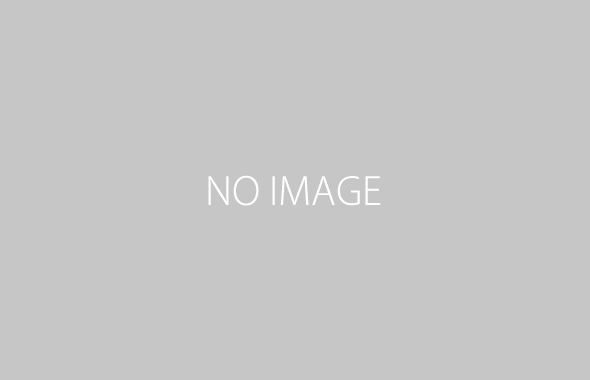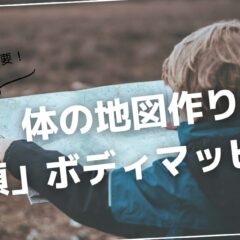腕の動き良くなると胴体までつながり、響きや音量がグンと良くなる!@PANよこしんとのレッスン
先日開催した第10回ドラムアレクサンダーテクニーク講座での、PANよこしんとのレッスンから1つご紹介します。
左腕のストロークについて
レッスンは「何を今日は聞いてみたいか、知りたいか」からスタートします。
よこしんが気になっているのが、左腕の振り方とのこと。
今でも充分に叩けているのは分かっていますが、理解を深めさらに向上したいわけです。
「チャドスミスみたい?」と聞くとちょうどdvdを見たとことだそうで意気投合!ライブが続くと腱鞘炎気味になるのも気になっている理由の1つでした。全国ツアーをするバンドにとっては、カラダへの負担は少なくしたいところですね。その取り組みの中の1つとして、左腕を振ることについて考えていくことにしました。
第1ステップ 情報集めして分析していく
今日の叩いてどんな感じか見せてもらう為に好きなように叩いてもらいました。
そこから見えたもので、2つ試してみれそうなアイデアが湧きました。
よこしんとしては、いつもに近い感じで叩けたけどやはりちょっと左手が気になるとのこと。
そこでスティックを構えた時の左腕の肩から肘までを考察。
スティックを構えた時、次のAとBどれに近いですか?

A.肘は胴体より後ろにある

B.肘は胴体真ん中 or 前よりある
セッティングやフレーズによって常に動き続けるドラマーにとって必ず腕はここ!というのはありません。
ですが、今回はリズムパターン叩いている時のスネアを叩く左腕にスポットを当てて考えてみました。
ではここで実験!!
1.写真Aのように肘を胴体よりも後ろにしてみて両手を振ってみます。
2.写真Bのように肘を胴体真ん中or前よりにして両手を振ってみます。
この実験は分かりやすいと思いますが、Bが動きやすいですよね。
写真Aのようにしていると、次の3つのことが起きやすくなります。
- 腕を振る前からすでに肩から肘までにかけて筋肉のスイッチがONになってしまいます。
- セッティングによっては、肘から先で腕を振ることになり肩や胴体は動きづらくなります。
- 左肘を過度に引いてしまうことで胴体にねじりも起きて腰の痛みや脚の動作にも影響します。
この日のよこしんから見えたものは、肘を胴体より後ろに引いて叩く【B】が多く見えました。
第3ステップ サポート&提案

提案1は写真Aバージョンで構えてからスタート。
※これはセッティングに影響が出るので、一気に変えることはオススメしないけど今回は実験でもあるので思い切ってやってもらいました。
すると、肩から肘にかけての動きが随分スムーズになって、腕全体が動き始めました。そして胴体の動きまでスムーズになるので、音の響きと音量が増えました。
この左肘を胴体より後ろに引いてしまう理由の1つとして、
「しっかり安定した音を出そう!」という気持ちが強い場合に起こるのかもしれません。
今回のように腕全体が動けるようになれば、胴体までつながりをもち音色に影響するのが分かりました。
レッスンでは叩き方や奏法を変えることはありません。
今うまくいかないことやもっと効率よくしたいことへの解決法として、
カラダが動きやすいように、本来のカラダの仕組みに協力できるようにしてあげること。
それには、カラダの仕組みを知ることも役に立つし、自分の考え方の癖やパターンを知るのも十分使えます。
提案2とサポート
そして2つ目の提案は、前にも紹介した頭の動きについて!
詳しくはこちら
→【ドラマーなら知っておきたいカラダのこと 動きやすくなるコツ】
腕のことだけに意識をしてしまうと、全体性が薄くなっちゃって部分的になってしまうんです。
「腕どうなってる!!!????」とすごく集中してしまってると、音への意識や周りも見れなくなって視野が狭くなります。
そこで、腕の動きが分かってきたらあとは頭を動けるようにするため(過去記事参照)に、今回は音の飛んでいく方向を見ながら叩くことにしました。

そうすることで、腕だけに過集中することなくカラダ全体がバランス取り始めてさらに腕の動きがスムーズになりました。
ドラムを叩き始めたら、音や曲のこと・表現することを考えることが、結果的にカラダの動きやすさにつながっていくのがよく理解できるレッスンでした。
よこしんだけ遅刻せずに来てくれたのでたっぷり時間をかけられたのもありますね(笑)
そんなよこしんがTwitterにあげてた凝縮されたコメント!
「ありがとうございました! 楽しかったー!」
こちらこそ、2度目の参加ありがとう!!
よこしんがドラムを担当する、
PANオフィシャルホームページ→http://pan-sound.com