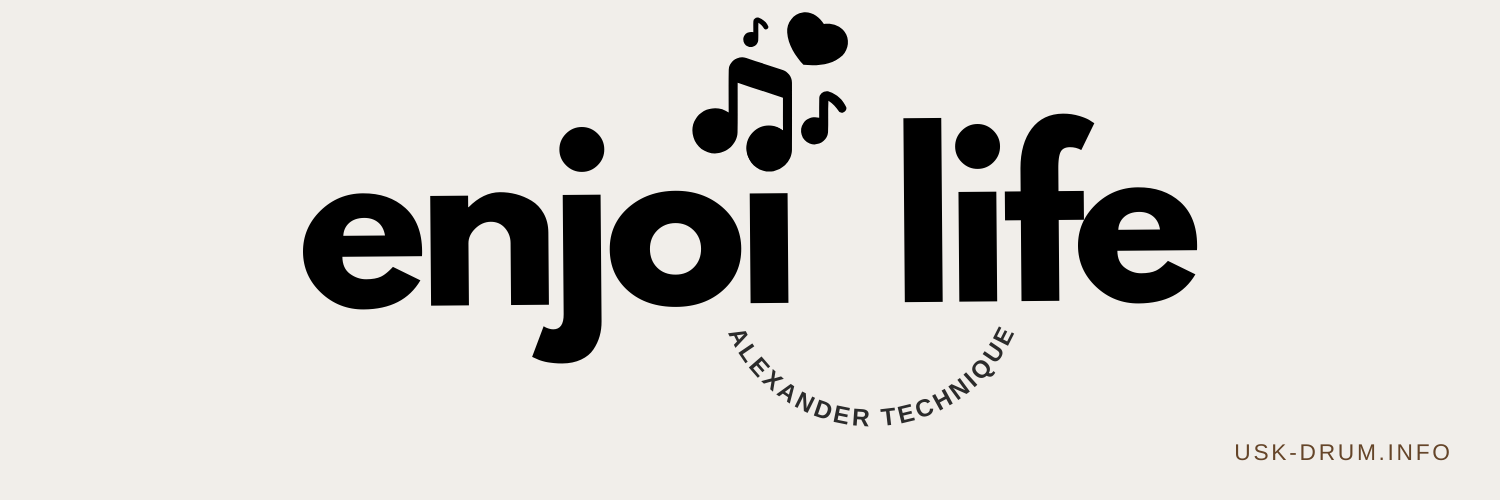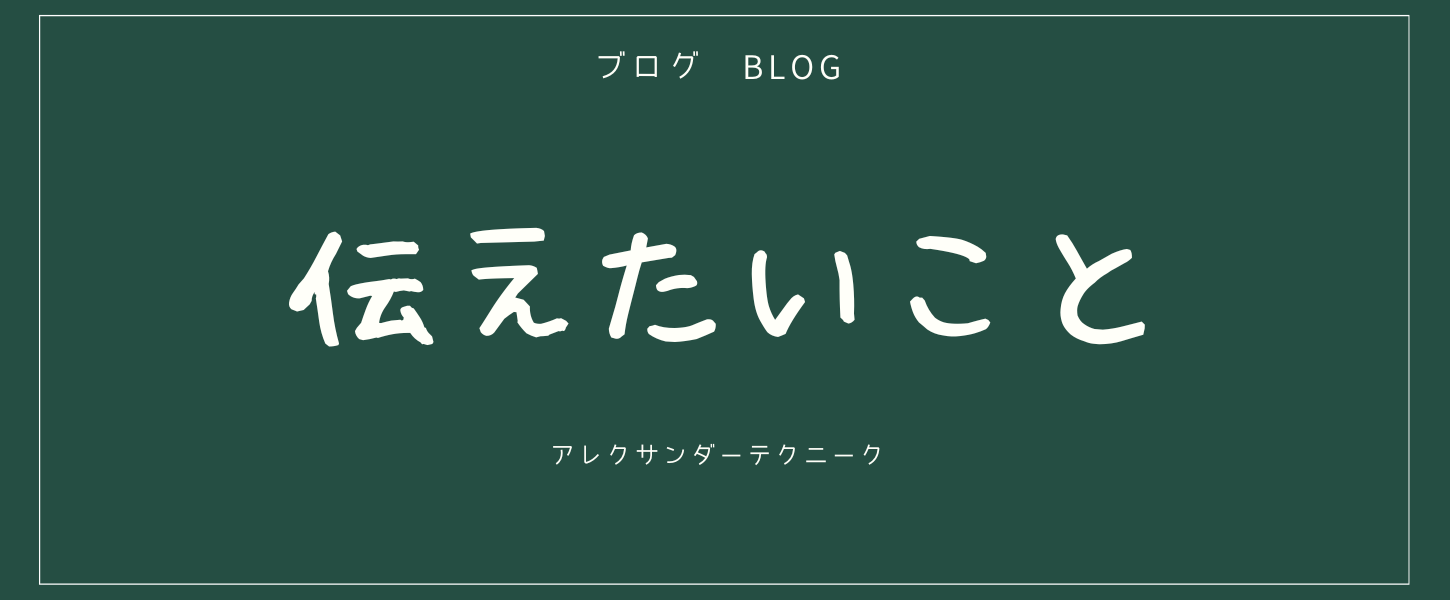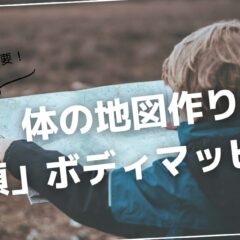「なんでわからないの?」がさらに「わからない」を増やすよね~指導を考える~
どうも、アレクサンダーテクニーク教師の山口裕介USKです。
今日は指導についてのお話です。
先日は「教える」ことを深めるためのティーチングWSを開催しました。
参加者は各楽器でのプロであり先生です。僕のアレクサンダーテクニークの視点から、「教える」を深めるためにレッスンでの観察ポイントや言葉の選択などを伝えている場です。
指導とはいえ、コミュニケーションが大切。先生と生徒の立場ですから、生徒側は先生に意見を言いづらいし、真剣に聞いてくれるので真に受けすぎてしまう人もいます。
広い視野を持って先生は生徒と接し、よく話し合うこと、そして言葉の選択が重要だなといつも感じます。
さてさて、前に気の合う先生と話題にしてたことがあって、まだまだ現場で聞く言葉があります。
「何がわからないか言って!」
「なんでわからないの?」
もうなくなってきているとは思うけど、まだまだ使われているみたいです。
学校でも親子関係でもある話でしょうね。
マイナスな思考へ追い込んじゃう
「なんでわからないの?」
言われてる側は追い込まれるし、やる気もなくなる。
「何」がわからないから、そもそも答えられへん。
「何が??」ってさらに疑問を増やしてしまうよね。反抗心も育ててしまうのかな。
この言い方をされたらマイナスな思考や感情にアクセスしやすい。
「何が悪かったのか?」
「何が間違っていたのか?」
「なぜ自分は答えられないのか?」
自分を責めることに向かうから、身体もこわばるし、呼吸も浅くなるし、目もまともに動けへんやろうね。
どれだけ頑張って、言葉を出したとしても、そんな思考から出た言葉は弱く、声も小さい。
先生側はもっとイライラするんじゃないかとまたビビってしまう悪循環。
生徒の分からないは先生の仕事
生徒がわかってないなら先生側に責任もある。
「何がわからない」について考えるのがそもそもの仕事ですからね。
同じ日本人とはいえ、生徒ごとに解釈は異なります。
同じ教え方、同じ言葉ばかりで伝えてるのであれば、数人に一人は届かないもんよね。
小学校、中学校、高校など大人数を教える場では個別に見ていくというのは大変時間がかかるし厳しいと中学の先生から聞いてるので、すべてに当てはめられるとも思えないけど。何か工夫はできるのかな、その辺りはまたその先生に聞いてみようと思う。
ただ僕らみたいにマンツーマンや少人数のグループでレッスンをするなら、その人の「何が」に合わせて言葉を選び、伝え方を工夫していくのはすごく大切やと思います。
「どこまでわかってるのかな?」
「何があったのかな?」
「何を思って演奏してたのかな?」
状況に合わせて確認をし、よく話し合いながらレッスンを進める必要がありますよね。
個々の音楽表現を育てていくんやからなおさら「個」を大切にしてあげたい。
「なにが分からないか言って!」
「なんで分からないの」
その場の状況にもよるのですべてとは思わない。
ただこの言葉を通してあらゆる視点で「教える」ことへの準備をしておきたいし、個人を尊重するためにもこれからも深く考えていきたいですね。
次の先生のためのワークショップが楽しみです。
今回もありがとうございました。
ほなまた!!
山口裕介USK