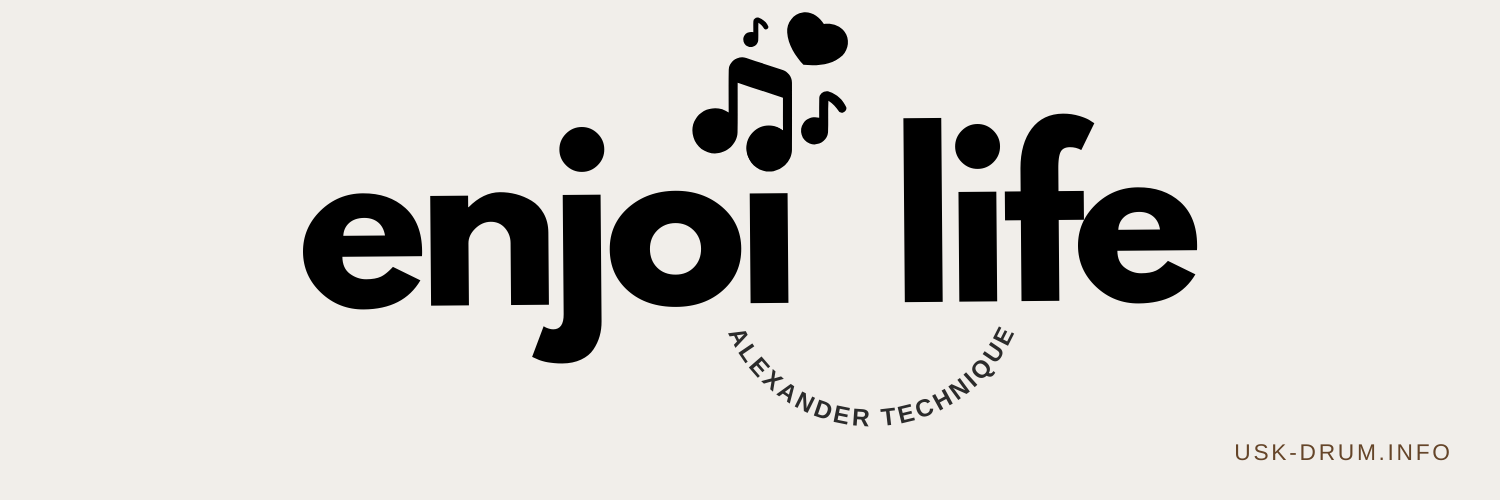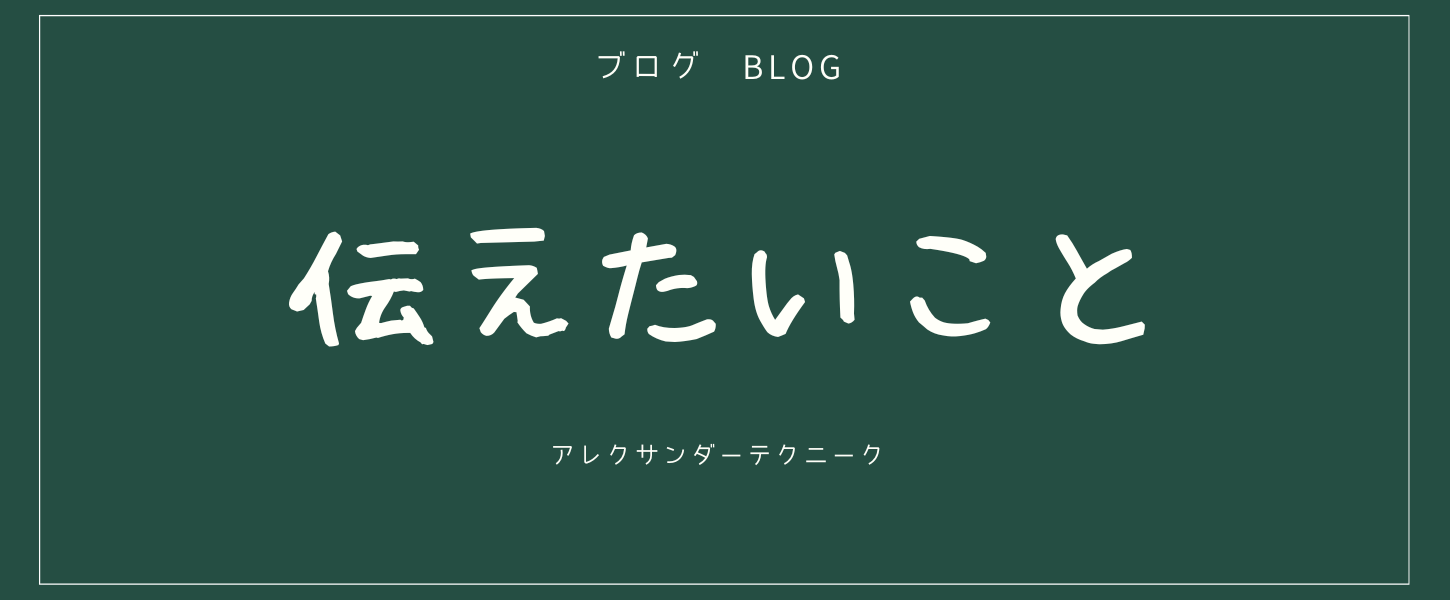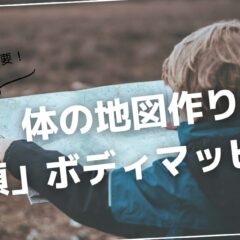「ちゃんとする」姿勢につながる意外と知らない言葉の影響力
どうも、アレクサンダーテクニーク教師の山口裕介USK(@usk_kimidori)です。
今日は、「音が出しづらくなってスランプ状態」に悩む高校生トランペットの生徒さんとのお話です。
アレクサンダーテクニークのレッスンでは何百何千回と管楽器奏者とレッスンしてますので、姿勢などの身体の不利な使い方で出しづらくなってるかは判断しアドバイスもできます。
身体の使い方だけでなくて、自分に使っている厳しい言葉が身体に影響を与えている場合もあります。
今回は「ちゃんとする」が動きの改善につながるヒントになりましたので、その辺りも含めてお伝えしていきます。
「隠れ呼吸筋」の使いすぎが発覚
まずは気になっている曲の一部を吹いてもらいました。
トランペットを構える直前に、背筋を伸ばして胸をはる、「気をつけ」のようにしていました。
そこだけやと問題はないんやけど、その状態を保ちながらトランペットを構えて演奏した。
USK「構えるまでに何を考えたのかな?」
生徒さん「音が出るか心配でちゃんとやろうと思って気合いれた感じです」
音が出しづらくなってきたんやから、気合いは入るよね。
ただその気合いは「吸いづらくないかな?」
ここで身体の解説です!!
背筋を伸ばして胸をはることで、次の写真にあるように「肩甲骨」が背骨の方へ寄ってきます。

肩甲骨を寄せるための筋肉の1つに「菱形筋」がありますが、これが隠れた呼吸筋。と僕は思ってるので、その説明をしときます。
胸を張るということは、
「菱形筋」が縮む→肩甲骨を背骨へ寄せていくことができる(青い矢印)
説明するよりやってもらった方が早いので、ちょっと実験。
背筋を伸ばして、肩甲骨寄せて、「はい吸って!」
吸えました?
肩甲骨を寄せすぎたら、肋骨が動きにくくなる。
肺が膨らむと肋骨も一緒に動きたいのに、そこを制限してるから入ってこないよね。
わざわざ自分で引き寄せて固めるのはスパルタすぎなのです。
この筋肉は脇の下ある「前鋸筋」や、首や肩につながる僧帽筋・三角筋にもご迷惑をかけてしまうので、まあ胸から腕にかけてブレーキをかけてしまうんですよね。
しかし今回のレッスンは解剖学ではなく視点を変えたところからアドバイスをしてみました。
注意しておきたい言葉が与える影響力
次の一言でまずは大きな第一歩となりました。
USK「ちゃんとするのやめてから吹いてみて♪」
手順はこんな感じ!
1.まずはちゃんとする(気をつけみたいなのね)
2.はい、終わり、休め~。
3.そのまま楽器を構えて演奏する
そうするとことで、音は耳にくる高い音というよりは丸み深みのある音に変わりました。
生徒さんは変な顔してましたけど。
それもそうで、ちゃんとしないで吹いたのに音が出て、しかも労力は減ったようなので気持ち悪いよね。
起きていた動きは、ちゃんとするのをやめた時点で、肩甲骨を寄せる動作が減って呼吸がしやすい状況になったから演奏できたからやね。
この取り組みで見えたのはちゃんとしていない方が音は出しやすくなったとも言えます。
演奏をする上で大切なこと
言葉1つで身体の動き方が変わる、わかりやすい例でした。
なんでも「ちゃんとしたい」気持ちもあるけど、まず出したい「音」が出せるように自分をコントロールするのが「ちゃんとする」こと。
今回のように演奏に不利な条件を作るのは、「ちゃんとしてない」にもなりかねないので切ないけど気をつけたいところ。
言葉の影響力がものすごく演奏姿勢に影響する、これは何度もレッスンで見ます。
何気なく使っている言葉が、自分を苦しめてしまうこともあります。
でも逆にうまくいくこともあるから、要は使い方なんですね。
言葉は見事に身体に影響しますから、逆に言えばその場に適した言葉を選んでいけば未来は明るくなる!
演奏しづらくなってきたり、姿勢に気がかりがあるならまずはメールでもいいのでぜひ相談してくださいね。
相談はこちらから→お問い合わせ
今日はこんな感じで、ありがとうございます。
ほなまた!!
山口裕介USK