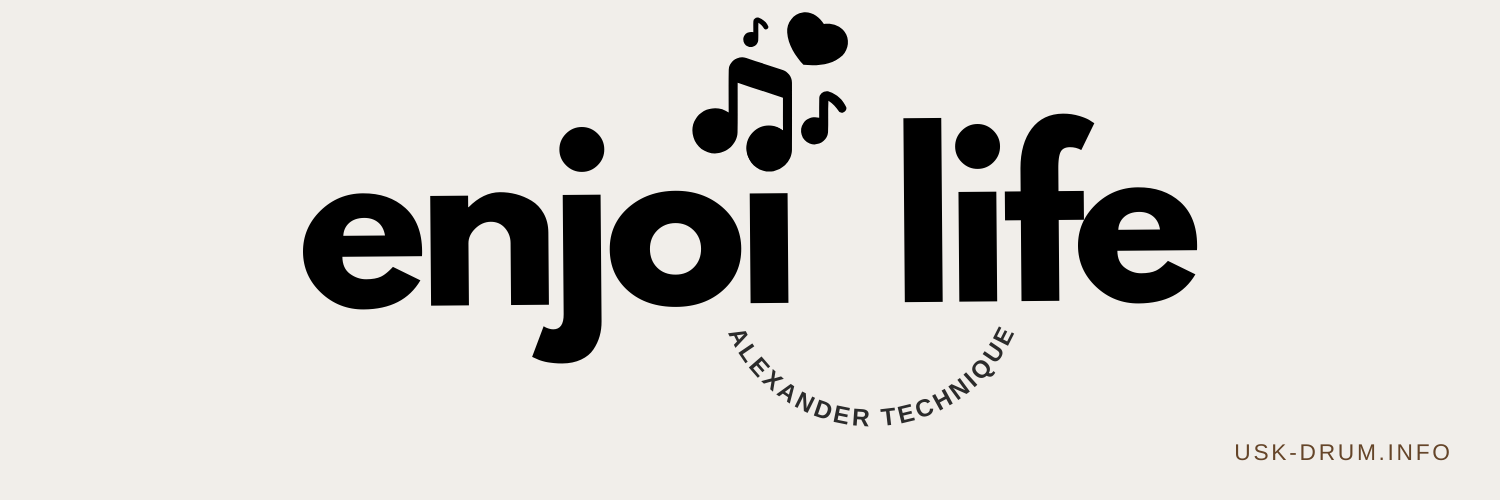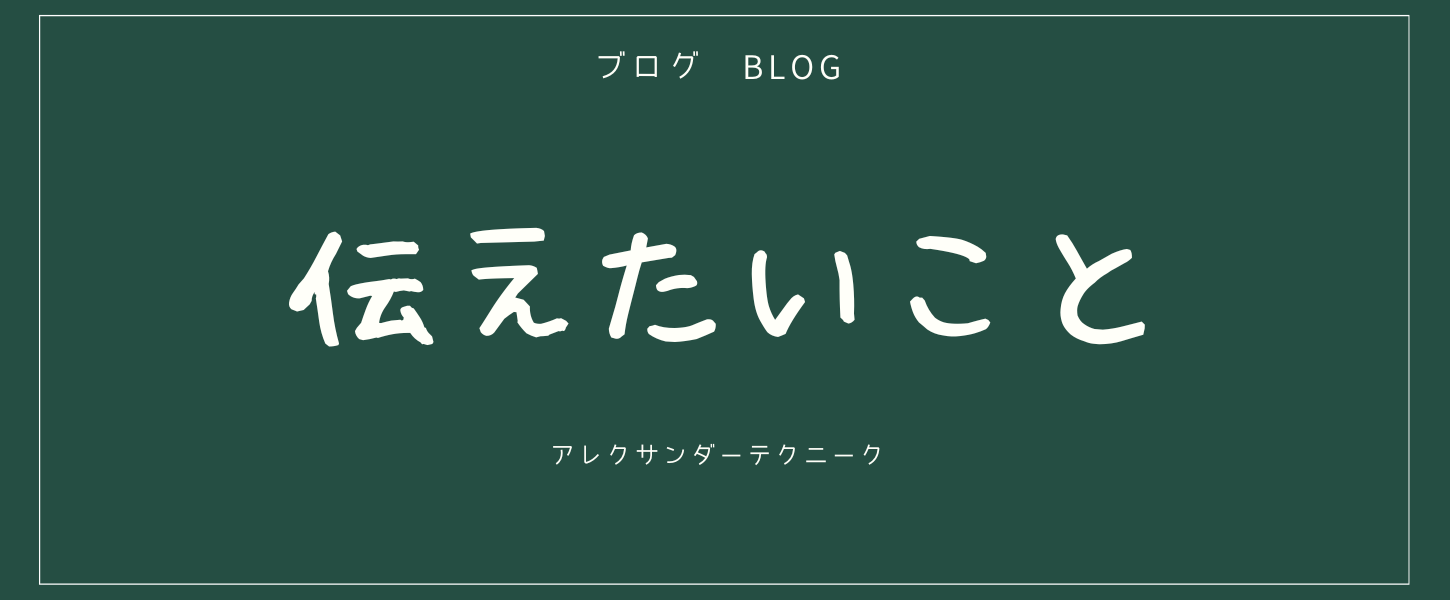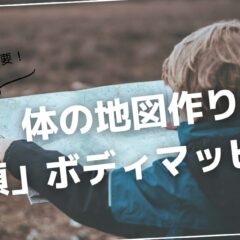脳科学から緊張対策!幸せになるホルモンを活性化させる
脳科学から見えてくる緊張対策「幸せホルモンってほんま幸せ」
どうも、ユースケサンタゴリラこと山口裕介 USKです。
さてさて緊張を味方につけるために、脳科学からの視点で何かやれることはないかと勉強してます。
今回もええ感じの脳内物質の話を見つけたのよ。
緊張対策ではなくてストレス対策などでよく出てくるから知ってる人はいるはずー。
さてこれまでお届けした専門用語たちは、
・扁桃体
・ノルアドレナリン
・アドレナリン
・交感神経
・副交感神経
とこれだけしか勉強してないけど、ここから色んな発想に広げられるヒントをもらえてるのよね。
レッスンでもさっそく伝え方も変わってきたしね。
脳科学でも立証されてることなら説得力あがるしで僕も生徒さんも納得しやすいから良いことだらけ。
今日も1つ頼りになりそうなことがあるのよ。
その名も「セロトニン」
幸せホルモンとも呼ばれてる、なんか期待大!!
脳内だけじゃなくて、腸にもけっこう存在するねんて。
だから腸を優しくしてたら幸せなるんやろか?ここはまた調べて試して効果あれば書いてみますー。
セロトニンはすっごく大事なリーダー的存在
では脳内に絞ってセロトニンことセロの働きは、
ドーパミンやノルアドレナリンが多すぎたら「どんだけー?とちょっと待った」をかける。
少なすぎたら「なんでやねん」とツッコミ入れて増やしてくれる。
上手に調整してくれるめっちゃ大事な役割やねん。
他にも、
・感情や気分
・依存、衝動を抑える
・ストレスに耐える
なんだか頼もしい。めっちゃ好きになりそう。
そして、チームリーダー的存在なので、かなり注目したほうが良さげ!!
このリーダーは、ノルアドレナリン 、アドレナリン、ドーパミンと個性的なメンバーが暴れ出さないようにバランスを取ってくれるからね。
いかりや長介的よね。
いいね、心と身体のバランスを取ってくれる大事な大事なリーダー。
ホンマみんなの幸せもリードしてくれてるよね。
さてさて、
これまで、扁桃体、ノルやアナが暴れ出したりした時の対処法をお届けしてきたよね。
色々と書いてきましたね。
これも過剰な緊張はほぐれてくるやろうけど、今回のセロにも活躍してもらいたいねん。
セロトニンを活性化させるための方法はまたお届けしますわ。
まだ試せてないから伝えるのもどうかなと思いますし。
ネットで調べたら沢山記事があるから、それも試してみるといいと思うー。
・朝日を浴びる
・朝食をとる
・トリプトファンを摂取
など、出てくるよ!!
しかし注目するのは!!
・リズム運動をする
・姿勢を正す
この2つに関しては、専門領域です♪
自分が持っている専門性と脳科学的緊張対策を組み合わせると・・・
おもろそーやん。
1つすぐ言えるのは姿勢は正そうとすると大半は呼吸しにくくなるので、この言い方はおすすめではないね。
twitterでこんな風につぶやいてみました。
姿勢を正すのが良いとは言われるけど、「気をつけ」のような形は演奏には不利🦍胸を張ったり肩甲骨を寄せながら呼吸するのは大変。
パフォーマンス上で姿勢を正すとするなら、呼吸しやすいのが大前提かな🍌— ユースケ・サンタゴリラ🦍USK山口裕介 (@usk_kimidori) 2018年7月7日
セロトニン活性法より大事なこと
今回ね、書いてて思ったことがあります。
適度な緊張にもっていく方法は科学的にもあるわけなのが分かった。
これが確実に自分に合うかはわからんけど、かなり現実的やと思う。
やるに越したことはない。
緊張だけやなくて、世の中にはやれば結果に繋がる方法は色々あるよね。
やっぱり最後は自分がそこへ向かうための行動ができるか?
「一歩ずつ進んでいけるか?」
普段からの行動をどうすれば、望んでることを達成しやすくなるか?
その辺も一緒に書いていきたくなるね。
世の中やれることは山ほどある!
どれからでもいいから、ピンッときたのから行動するのもありよね。
というわけで、引き続き脳科学視点からの勉強は続けてみて、使いたくなるようなのがあればお届けしますね。
では今日はこの辺で!
いつも最後まで読んでいただきありがとうございます。
ほなまた!!
ユースケサンタゴリラ 山口裕介USK